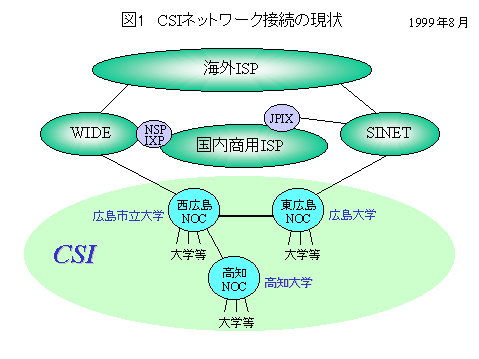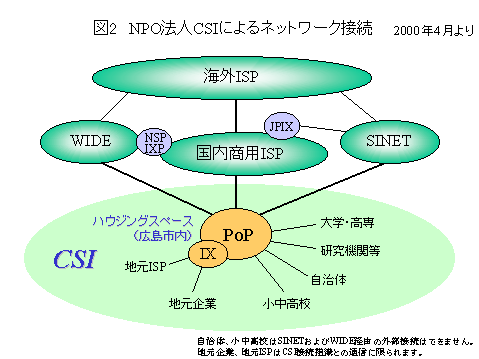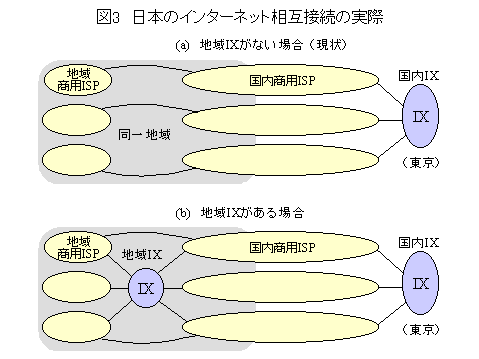|
平成11年8月18日 特定非営利活動法人
|
|
|
また、新たな事業として当地域におけるインターネットの相互接続(地域IX)を実現します。CSIには、過去5年にわたる2つの学術系ネットワーク(WIDEおよびSINET)との本格的なマルチホーム運用の実績があり、インターネット相互接続に必要な基礎を築いてまいりました。地域IXの実現およびその発展は、地方分権の実現にも例えることができ、インターネットの世界を大きく変えることになります。CSIは日本で初めてNPO法人による地域IX実現をめざします。中立・公平な立場で相互接続機能を提供することにより、当地域のインターネット利用をさらに促進します。
2.2 研究研修事業これまでも著名な講師を招いた講演会、最先端技術のシンポジウムや講習会を多数開催してきました。例えば、日本インターネット技術計画委員会(JEPG/IP)が主催するインターネット技術者の全国会議IP Meeting '96(1996年12月2〜4日、広島国際会議場)を共催しました。また、小中高校でのインターネット利活用を促進する研究会を発足し、教育現場での試行的実践を支援し、多くの成果を上げてきております。例えば、文部省と通産省が推進した100校プロジェクト(1994〜1996年)、新100校プロジェクト(1997〜1998年)において中国・四国地域の11校のインターネット接続を支援しました。さらに、ネットdeがんすプロジェクト(1998年)をCSIが中心となって実施し、1999年6月12日にはその成果発表会を開催しました。今後は活動をより一層充実させ、コンピュータネットワークの技術及び利用に関する普及啓発を図ります。 一方、CSIが発足した当時からインターネットに関連する最先端技術の研究開発を進めるとともに、その応用についてシンポジウムなど様々な機会を捉えて広く紹介してきました。1995年8月6日には、インターネット上のマルチキャストと呼ばれる放送技術を使用し、広島平和公園で開催された平和記念式典の模様を、動画像、5ヶ国語音声(英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポーランド語)、文字(英語)にて全世界向けにリアルタイムで発信しました。これは、当時としては高い技術を必要とする極めて画期的な試みでした。今後、コンピュータネットワークの接続技術及び利用技術に関する研究・開発をより一層推進します。広島県が推進する情報トライアングル計画や郵政省が推進する列島縦断ギガビットネットワーク等へ参加し、共同研究を通して、次世代インターネットプロトコル(通信規約)の研究開発等を進める予定です。 3 協議会の活動意義3.1 地方におけるインターネット接続インターネット接続は、もはや商業基盤に乗った企業活動であるとの見方もあります。確かに、商用インターネットサービスプロバイダ(商用ISP)のサービスエリアは全国各地に拡大し、単にインターネットへ接続するというレベルでは地域的な差異は小さくなったようにも見えます。しかし、日本ではわずか5年前に開始された商用インターネット接続事業は、その急成長と淘汰の過程で品質よりもコストを重視する傾向が強く、特に事業者間の相互接続については対応が後手に回ってきました。そのため、事業者間相互接続は東京一極集中となり、接続事業者が異なる場合、同一地域の組織間通信がすべて東京経由となっています(図3参照)。図3(a)に示す現状のままでは以下のような問題を起こします。 |
|
|
3.2 普及啓発および研究開発文部省は2001年までにすべての学校をインターネット接続する方針で、現在準備が進められていますが、ハード面のみ急速に整備したのでは効果的な利活用ができないばかりか、大きなトラブルを起しかねません。CSIはこれまで小中高校については、100校プロジェクトでのインターネット接続支援と同時に学校教員を中心とした研究会の支援を行ってきました。さらに、その成果を生かしたCSI独自のネットdeがんすプロジェクトを実施し、大きな成果を上げており、全国的にも注目されています。これらの経験を踏まえ、今後CSIでは小中高校へのインターネットの円滑な導入を目指し、様々な試みを行う予定です。 インターネットの接続技術開発は日進月歩で進められており、特に米国では超高速通信回線と新しい通信プロトコル(通信規約)を使った次世代インターネット(NGI)計画が1997年頃から政府主導で推進されています。日本でも1999年より郵政省が中心となって列島縦断研究開発用ギガビットネットワークが開始されるなど、次世代のインターネット技術の研究開発が進められています。CSIではギガビットネットワークの共同研究に参加し、最先端技術の研究を進めています。また、広島県が推進する情報トライアングルを活用し、次世代インターネット実験等を実施するなど、地域における新しい情報通信基盤に関連する研究開発を積極的に行う予定です。 3.3 NPOによる活動の意義インターネットは情報通信のインフラであり、道路や水道と同様、現在すでに大学や企業等の必需品となっていますが、近い将来、個人の生活のためにもなくてはならないものとなるでしょう。電話やFAXは受益者の概念がはっきりしているサービスで、バスやタクシーに乗ることに対応しますが、インターネットはその上で様々なサービスが行われるため、道路に対応させるのが自然です。道路の整備であるとすれば、インターネットは自治体等が税金の一部を使って整備すべきとも考えられます。特に、相互接続点の設置、運用は、個別のサービスから非常に遠く見えにくい部分であり、意図的かつ計画的に整備しなければいつまでも整備されない危険性があります。岡山県などいくつかの地方自治体は、積極的に地域IXの試行的な運用を始めています。しかし、急激に変化するインターネットの世界で、その運用を任された第3セクター等が、状況の変化に柔軟かつ適切に対処することは困難な点が多く、さらに地方財政が非常に厳しい現在、新たな財政負担は極めて困難な状況にあります。 特定非営利活動法人(NPO法人)は、このような状況で第3セクター等に替わる枠組みとしても注目されています。すなわち、自治体が抱え込んだ重過ぎる荷をNPOで分担するという考え方です。地方における新しい公共事業推進のあり方としてもCSIの試みは注目されており、現在他の幾つかの地域でも地域IXなどのインターネット相互接続事業を主な目的としてNPO法人化が検討されています。 4 諸費用について1993年に任意団体として協議会が設立して以来、協議会は会員組織および運営委員を中心とした個人のボランティアにより運営されてきました。インターネット接続についてはNOCまでの回線および接続装置は各接続組織の負担、NOC設備や協議会全体で必要なバックボーン回線費用(一部)等はNOC設置組織の負担、日本国内および海外への接続については学術系組織に限りWIDEおよびSINETの協力を求めるなどしてきました。また、接続の維持管理はNOC技術担当者による献身的な支援に支えられてきました。しかし、インターネットがインフラとなってきた現在、以下のような問題を抱えています。
これらに対するひとつの解がNPO法人の設立であり、2000年4月より運用を開始する新しいネットワーク接続形態だったわけです。 新しい協議会では、接続組織(非営利組織の団体正会員に限る)とPoP間の通信回線契約、PoP設置場所の確保、PoP接続機器の準備、商用ISPによる国内および海外接続性の確保、基本的な接続維持管理(外注)等をCSIとして行います。そのために必要な経費は、接続料、設備利用料などとして接続組織に負担して頂きます。今回新たに開始するIX事業については、IX接続組織(団体正会員に限る)からPoPまでの通信回線はIX接続組織の責任で敷設して頂き、IX設置場所の確保、IX接続機器の準備等をCSIとして行います。そのために必要な経費は、設備利用料などとしてIX接続組織にご負担頂きます。また、会員(個人正会員、団体正会員、賛助会員)の会費は、すでに述べたインターネット接続事業、研究研修事業などを支援するため必要なCSIの管理運営費用として使用されます。 以上のようにCSIはインターネット接続事業についてこれまでと異なる方針を打ち出し、より安定したインターネット接続、相互接続点の運用をめざします。しかし、その基本はこれまでどおりCSIの趣旨に賛同した、技術的知識を持つボランティアを中心とした非営利組織です。したがって、商用ISPのように技術者を雇用する等の経費をかけないにもかかわらず、最高水準の技術支援がボランティアにより提供されます。また、インターネット接続事業と研究研修事業は密接な関連を持ち、協議会全体として極めて公益性の高いインターネット普及啓発活動が展開できます。 5 むすびCSIはその活動意義を理解して頂き、ご協力頂ける会員(個人正会員、団体正会員、賛助会員)の皆様によって支えられています。また、会員でない個人の方でもボランティアとしてお手伝い頂くことができるようになっています。 CSIの活動にご賛同いただける幅広い皆様方の参加及びご支援ご協力を切にお願いいたします。 中国・四国インターネット協議会 (CSI) 事務局 URL: http://www.csi.ad.jp/ 
|